第5話「恋の成就はまかせて!~「業平井戸」~」
あたみ歴史こぼれ話(本編)
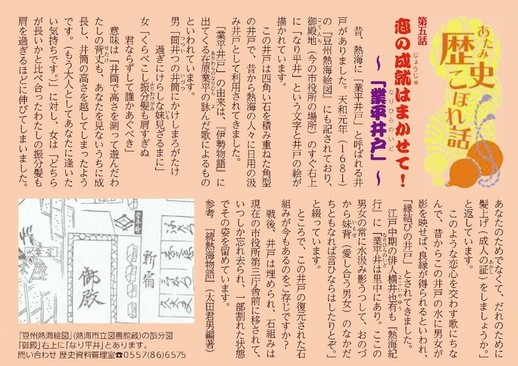
※広報あたみの原本をご覧になりたい場合は、
以下のリンク先からご覧ください。
あたみ歴史こぼれ話―本編の後に
このコーナーでは、「あたみ歴史こぼれ話」で
掲載しきれなかったことを中心にご紹介します。
本編を読み進んだ後に、ご覧ください。
画像の保存、複製及び使用は禁止といたしますのでご遠慮ください。
「業平井戸」(なりひらのいど)の名称は、平安時代に著された
『伊勢物語』(在原業平を思わせる男を主人公とした和歌にまつわる
短編の歌物語集)に由来するといわれています。関係する物語の一部を
紹介しましょう。
「 二十三
むかし、田舎わたらひしける人の子ども、井のもとに出でてあそびけるを、
大人になりにければ、おとこも女も恥ぢかはしてありけれど、おとこは
この女をこそ得めと思ふ。女はこのおとこをと思ひつゝ、親のあはすれども、
聞かでなんありける。さて、この隣のおとこのもとよりかくなん。
筒井つの井筒にかけしまろがたけ過ぎにけらしな妹みざるまに
女、返し、
くらべこし振分髪も肩すぎぬ君ならずして誰かあぐべき
などいひいひて、つゐに本意のごとくあひにけり。」
(出典:日本古典文学体系9『竹取物語 伊勢物語 大和物語』 岩波書店)
「業平井戸」の話は「歴史こぼれ話」の本文にも書いたように、18世紀
(江戸中期)に活躍した横井也有(尾張藩の要職を歴任した文武両道の武士で、
俳人としても有名)も『熱海紀行』に記しているわけですが、すでに元禄12年
(1699年)に鈴木秋峰が著した『豆州熱海地志』でも紹介されています。
また、大正時代に書かれた『新撰熱海案内』(齋藤要八著)では、
熱海の名所の一つとして、以下のように紹介されています。
「業平井 新宿の道端に在り。昔は業平朝臣の詠歌にちなみて、男女共に
井水に影をうつして、婚姻の縁を結びしことありしも、今は斯る風習もなく、
只故址を存ずるのみ。
豆ひきの影や井筒のまめをとこ 横井也有」
(出典:『新撰熱海案内』 熱海温泉場旅館組合(大正14年10月1日 三版))
また、地図では、本文に掲載した天和元年(1681年)の『豆州熱海絵図』
(現存する熱海の最も古い絵地図)の他、元禄8年(1695年)の絵地図
『豆州熱海湯治道知辺(あたみとうじみちしるべ)』にもはっきりと描かれています。
ですから、300年以上も前から人々に知られ、語り継がれているロマンチックな
井戸の話ということになります。
「歴史こぼれ話」の本文に掲載したのは、『豆州熱海絵図』の一部(部分図)ですが、
このページでは絵地図の全体を紹介します。
御殿(現熱海市役所の地)や熱海村の温泉宿、伊豆山権現(現伊豆山神社)の
様子などが描かれていますので、ご覧ください。
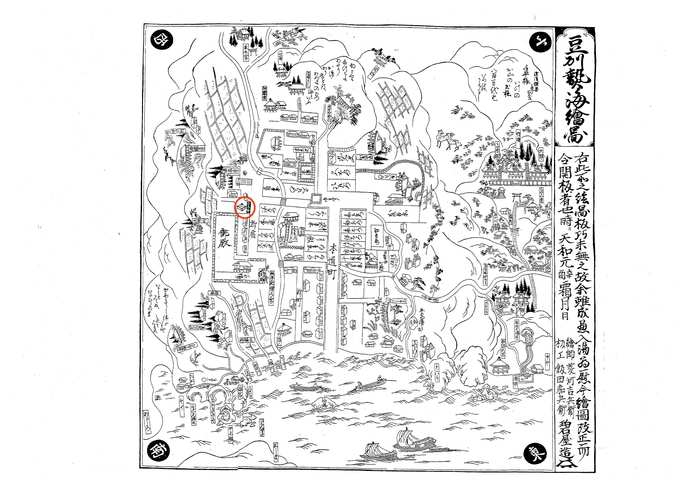
※大きい画像をご覧になりたい場合は、下の添付ファイル(「豆州熱海絵図」)からご覧ください。
-
「豆州熱海繪圖」(大きな画像で見ることができます) (Jpeg 811.5KB)

※地図南西側中央に描写のある「御殿」(御殿地。今の市役所の場所)の右上に「なり平井」と書かれた井戸(「業平井戸」)があります。(赤丸をつけた場所が「業平井戸」です。)
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 生涯学習課 歴史資料管理室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6232ファクス:0557-86-6606
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
