第2話「人車鉄道にも軽便鉄道にも乗りたくない!」
あたみ歴史こぼれ話(本編)
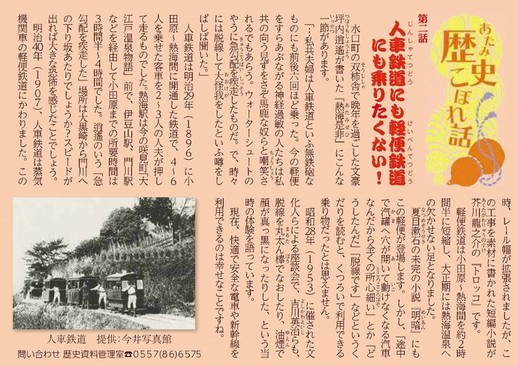
※広報あたみの原本をご覧になりたい場合は、
以下のリンク先からご覧ください。
あたみ歴史こぼれ話―本編の後に
このコーナーでは、「あたみ歴史こぼれ話」で
掲載しきれなかったことを中心にご紹介します。
本編を読み進んだ後に、ご覧ください。
画像の保存、複製及び使用は禁止といたしますのでご遠慮ください。
【「豆相人車鉄道」について】
この鉄道計画に参加した人々は、茂木惣兵衛、高島嘉右衛門、雨宮敬次郎、
大倉喜八郎、平沼専三などの実業家と、石渡喜右衛門(富士屋)、
樋口忠助(気象万千楼)、露木準三(香霞館)などの当時の熱海の
一流旅館主でした。
開業は、熱海から吉浜までの間が明治28年(1895年)7月、吉浜から
小田原までの間が明治29年(1896年)3月で、全長25キロメートルの単線。
熱海と小田原(早川口)の間に伊豆山、門川、吉浜、城口、江の浦、
米神などの停車場が設けられ、路線の約半分の13キロメートルは
熱海街道(ほぼ現在の国道135号線)上を通っていました。
熱海・小田原間の運賃は、上等車1円、中等車60銭、下等車40銭で
明治33年(1900年)9月の運賃表によると、1日6往復運転されました。
【「軽便鉄道」について】
人車鉄道のレール幅を610ミリメートルから762ミリメートルに拡げ、
明治40年(1907年)12月から蒸気機関車1両、客車(定員36名)1両の
編成で営業運転を始めました。大正2年(1913年)4月の時刻表によると
1日7往復運転され、熱海・小田原間の所要時間は2時間20分ほどで、
例えば新橋を午前8時30分に出発すると、国府津と小田原で乗り換えて、
午後1時18分には熱海に着くことができました。
(当時の東京・熱海間の所要時間は5時間弱でした)
大正9年(1920年)、国鉄熱海線が建設されることとなったため、
軽便鉄道は政府に補償買収され、熱海線工事の進行とともに運転区間が
短縮されていきましたが、最終的には対象12年(1923年)の
関東大震災により線路や停車場が壊滅的打撃を受け、廃線となりました。
(出典:豆相新聞 明治44年6月27日発行)
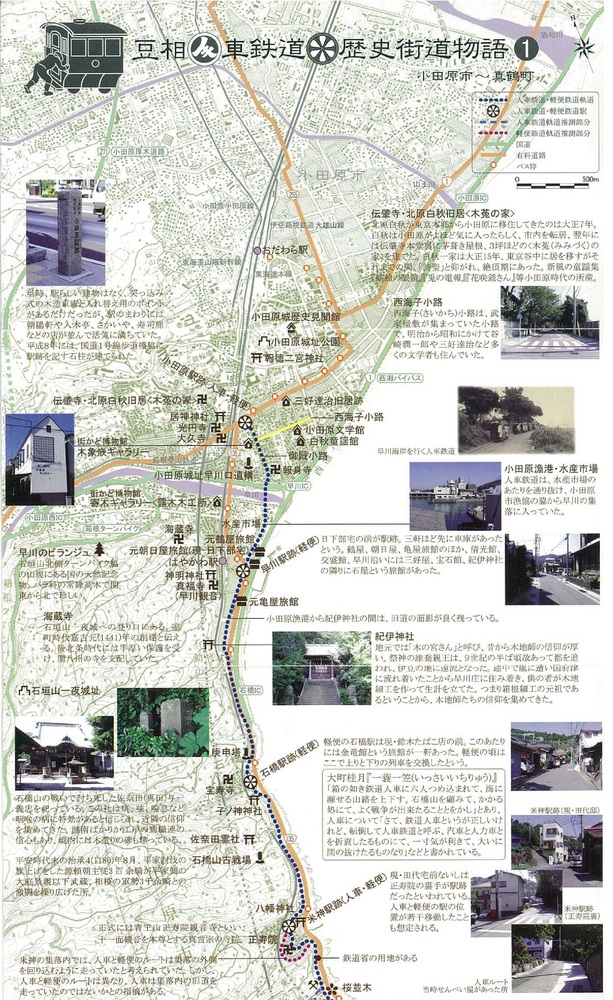
(出典:『ガイドマック 豆相人車鉄道歴史街道物語』)
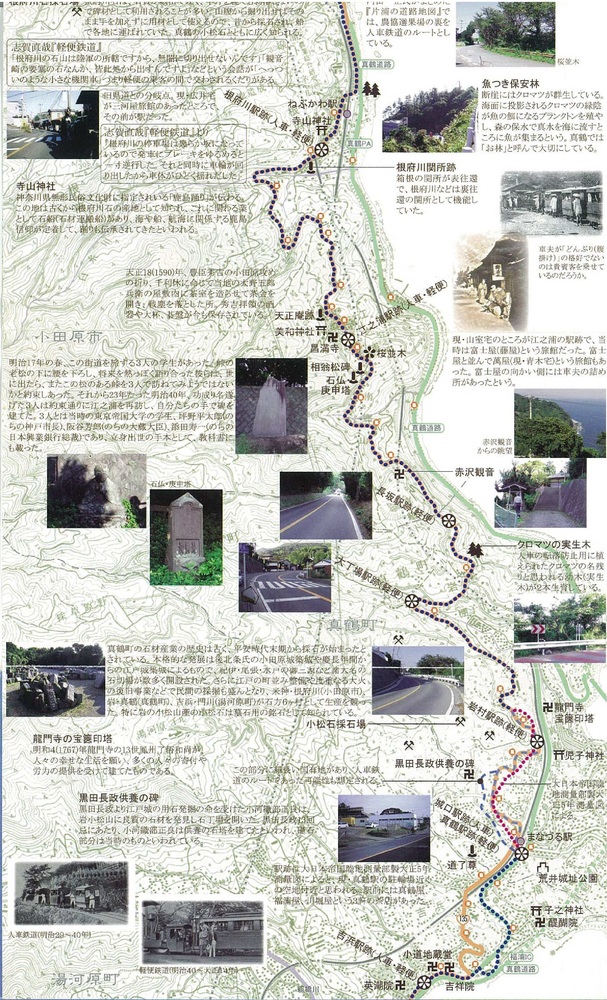
(出典:『ガイドマック 豆相人車鉄道歴史街道物語』)
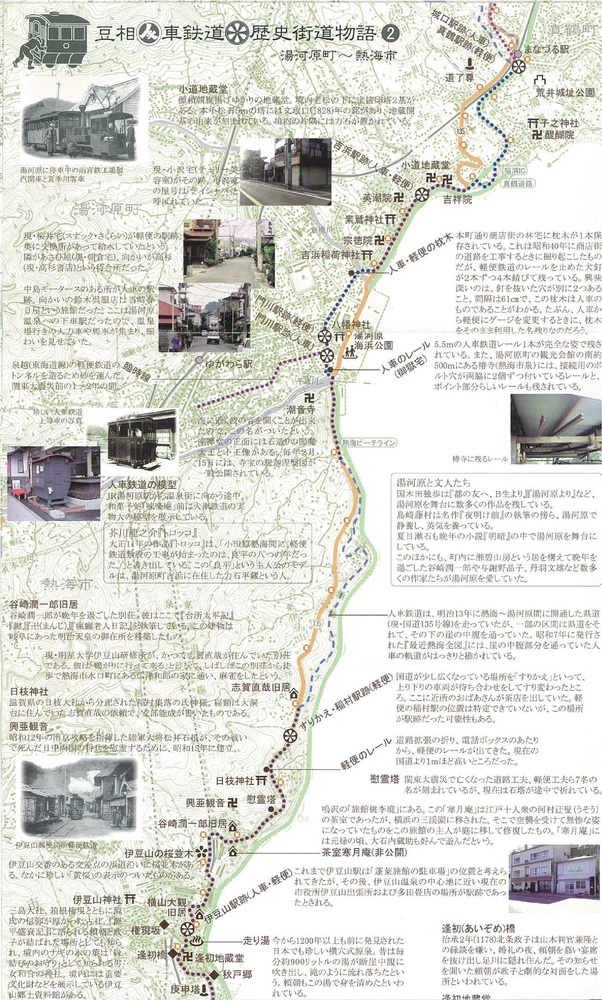
(出典:『ガイドマック 豆相人車鉄道歴史街道物語』」)
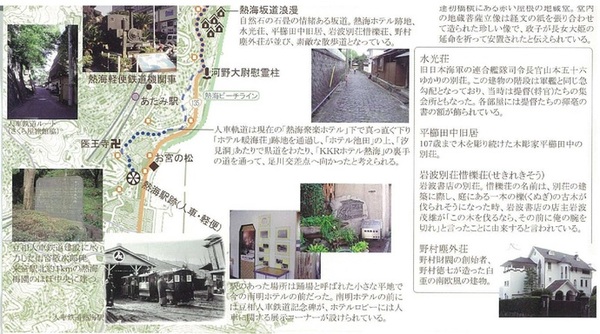
(出典:『ガイドマック 豆相人車鉄道歴史街道物語』」)

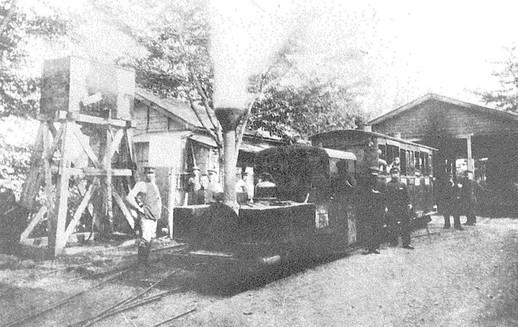
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 生涯学習課 歴史資料管理室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6232ファクス:0557-86-6606
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
